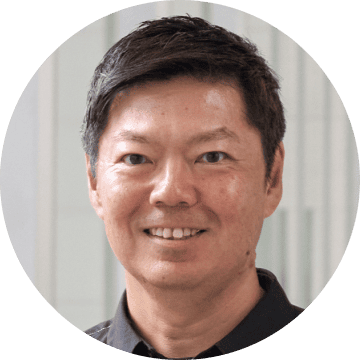Contents
半導体を学んだ学生が半導体業界に進むとは限らない? その理由とは
01
2025.10.29
- Text
- :武者良太
- Photo
- :平郡政宏

私たちの生活に欠かせない存在として、需要が高まり続ける半導体。その開発と生産の舞台裏には、多くの技術者が携わっています。そんな中、近年指摘される人手不足の問題は半導体業界にとっても他人事ではなく、一朝一夕で育てることができない技術者・研究者といった理系人材をどのように増やしていくのか、またそうした人材のキャリア形成をいかに支援していくのかは、日本全体においても重要なテーマとなっています。
そこで今回は、理系人材と企業をつなぐマッチングサービスを提供するA-Co-Labo代表の原田久美子さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)の人事担当である藤谷和弘さん、末廣優紀菜さんに、半導体業界で理系人材が成長し活躍するために、どのような課題があり、どんなサポートが求められているのかを語っていただきました。
半導体業界では需要拡大に伴い人材不足が深刻化していますが、理系学生の多くが「難しそう」「よくわからない」と感じ、他業界を選ぶ傾向が強まっています。A-Co-Labo代表の原田久美子さんやソニーセミコンダクタソリューションズ(SSS)の人事担当者によると、半導体業界は情報・電子系に限らず多様な専攻の人が活躍できる場であるにもかかわらず、業務内容が見えにくいことが敬遠される要因になっているそうです。一方で、SSSでは「世界一の技術に関わりたい」と志す学生も多く、魅力発信と若年層への啓発が重要とされています。子ども向け科学教室などを通じて、半導体の面白さを伝える取り組みも進められています。
情報・電気・電子専攻だけじゃない! 多様な人材が求められる半導体業界

——全国的に人手不足が指摘される中で、半導体業界でも人材獲得競争が加熱していると聞きます。現況はどうなのでしょうか。
末廣:現代社会において半導体は不可欠なものとなっており、半導体の設計開発から製造に至る各分野で、⼈材獲得競争がいっそう激しくなっているのが近年の状況です。
また、そうした人材需要の高まりに加え、別の側面の課題も競争に拍車をかけています。私はSSSの新卒採用を担当しており、多くの学生の方と接するのですが、「半導体=よくわからない、難しい」というイメージを持っている方が多くいます。そのため、半導体業界がキャリアの選択肢に挙がりにくく、理系学部で学び技術的な素養を身につけた学生であっても、他業界を選んでしまうケースも少なくありません。
原田:確かに、半導体業界は”ブラックボックス”ととらえられてしまう面がありますね。上流から下流まで、およそ600の製造工程があり、具体的に何をしているのかが外から見えにくい。
逆に、それだけあるからこそ、自分のスキルを活かせるチャンスがあるという点を、どれだけ学生に理解してもらえるかが大事なのかなと思います。半導体業界は、必ずしも情報系や電気、電子専攻でなければいけないわけではなく、それ以外の分野の専攻者でも活躍が可能な、さまざまな職種がありますから。
藤谷:半導体に対する理解を深めてもらったり、業界との距離を縮めたりする施策が大事になっていますよね。
——原田さんは、修士課程の修了後、化学メーカーで半導体企業向けの開発に従事されたそうですが、その進路はご自身で明確に描いていたのですか。
原田:いえ、私も初めから半導体業界をめざしていたわけではないんです。大学院時代は「固体触媒」といって、化学反応を早めたり、特定の反応を起こしやすくしたりする研究をしており、就職先として検討していたのは、自動車メーカーや触媒メーカーでした。それが、縁あって半導体製造に使われるフォトレジストのメーカーに勤めることになり、約6年ほど研究開発に従事することになったんです。
先ほどブラックボックスというお話もあった通り、半導体のさまざまな工程や、業界の仕組み、面白さなど、入社してから初めてわかったことが、たくさんありました。
半導体を研究してきたのに、半導体業界を選ばない?

末廣:原田さんにうかがいたいのですが、近年、半導体を研究してきた学生も、進路に半導体業界を選ばないケースがみられるように思います。この要因はどこにあるのでしょう。
原田:そのお悩みは、半導体業界だけじゃなく、近年のものづくり業界全体の”あるある”だと感じています。理系の大学・大学院を卒業したのち、従来は文系出身者が多いと考えられたコンサルティングファームやIT、ベンチャーキャピタルなど、”トレンドの業界”に進むケースが増えています。もちろん、本人が進みたい道を選ぶのが一番ですが、「ものづくり」業界に興味を持つ機会が減っていることが、要因の一つではないかと考えています。
日本の「ものづくり」は、グローバルでの競争力が落ちていると言われる分野もありますが、依然として高い技術力や対応力などの強みを持っている。普段の生活が、こうしたさまざまな技術に支えられていることを実感する機会が少ないために、業界への魅力を感じないままになっているのではないでしょうか。
藤谷:日本の半導体業界は1990年代後半ごろから業績低迷が続き、大きな業界再編も進むなど厳しい状況が続いていました。しかし、現在はデジタル化の進展などにより需要が高水準で推移しており、今後のさらなる成長が期待されています。われわれも含め半導体業界の採用担当者は、そうしたポジティブな要素を積極的に発信していく必要があると思っています。
グローバル規模で自分の力を試せる面白さ

——一方で、半導体業界に魅力を感じて志す人材も、もちろん多いかと思います。そうした方々は、どのような志望動機を持っているのでしょうか。SSSの場合はどうですか?
藤谷:志望者と面接でお話しすると、「世界一の技術に関わる仕事がしたい」と言ってくださる方が多いですね。SSSは、イメージセンサー市場で、50%を超える世界トップのシェアを誇っています。イメージセンサーは、スマートフォンはもちろん、自動車や工場などさまざまな分野での活用が今後も大きく期待されており、その製造に関わることは、多岐にわたる分野をグローバル規模で支える仕事ともいえると思います。そんな舞台で、自分の力を試せることに魅力を感じてもらえているようです。
末廣:そうですね。応募してくださる方には半導体業界やSSSの魅力が伝わっているとは感じるのですが、いかにその母数を増やしていけるかが、今後の私たちの課題です。
原田:スマートフォンやゲーム機など、これからを担う世代が小さな頃から触れてきた身近なデバイスが、半導体で支えられていることをどれだけ伝えられるかが鍵ですよね。”刷り込み”じゃないですが、それこそ小学生ぐらいから伝えることができれば、そうした人材が育つ土壌が生まれるのではないでしょうか。
実は私、「技術者・研究者になるきっかけを地域で作りたい」という思いで、個人事業として⼦ども向けの科学教室を行なっているんです。そこで、たとえばドローンの説明をする際に「ドローンの脳みそは半導体なんだよ」という話をすると、とても興味を持ってもらえます。もちろん難しい技術などには触れないのですが、⾃分がこれまで培ってきた何かしらの知⾒を次世代に伝えることで、魅力を知ってもらうきっかけになればと思っています。
—— 次回は原田さんに「理系人材と企業それぞれがマッチングに求めていることと、起きている課題」について、お話をうかがいたいと思います。
この記事にリアクションする