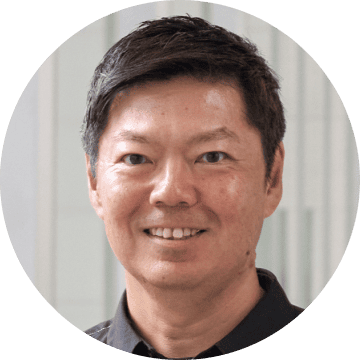Contents
技術者・研究者は、新たな場に挑戦しづらい? その解決に必要なこと
02
2025.10.29
- Text
- :武者良太
- Photo
- :平郡政宏

理系人材と企業をつなぐマッチングサービスを提供するA-Co-Labo代表の原田久美子さんと、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)の人事担当者2名による鼎談。第2回は原田さんに「理系人材と企業それぞれがマッチングに求めていること」をうかがいつつ、そこで起きている課題解決に向けて取り組むべきことは何かについて語り合いました。
原田久美子さんは化学メーカーで半導体向けフォトレジストの研究開発に携わった後、出産を機に退職し、再就職の難しさや研究者の非正規雇用の多さに課題を感じ、2020年にA-Co-Laboを設立しました。A-Co-Laboは、企業と研究者・技術者が交流し、互いのギャップを理解し合う場を提供することで、新たな連携やイノベーションを促進しています。登録者は自分の研究を異分野で活かしたい、挑戦したいというニーズを持つ方が多く、企業側も新しい発想を得るために研究者を求めています。また、ソニーグループでは「キャリアプラス制度」により社員が他業務に挑戦できる仕組みを整え、柔軟なキャリア形成を支援しています。こうした制度や仕組みが、技術者の新たな挑戦を後押しする鍵になるとされています。
技術者・研究者のキャリア形成を阻む壁
——原田さんは、化学メーカーで半導体企業向けの開発に携わったのち、どのようにA-Co-Labo起業に至ったのですか?
原田:私は大学院で化学系の工学部の研究科を修了し、化学メーカーで、半導体に使われるフォトレジストの研究開発を約6年行い、出産のため退職しました。当時はまだ子育てとの両立が難しく、また半導体業界の開発サイクルの速さもあり、ライフイベントで研究開発の仕事を諦める女性も多かったです。
1年半ほど専業主婦をしたのち、小学校の理科支援員として少しずつ社会復帰を行い、大学で研究員として再出発しましたが、募集があるのはプロジェクト型の非正規雇用ばかりでした。研究者としてのキャリアを歩むためにこうした雇用のあり方を否定するわけではありませんが、私のように40歳で改めて社会に出ようと思ったとき、雇用の間口があまり用意されていないことに疑問を抱きました。
一方で、採用される側の研究者も、大学の研究現場しか知らないまま企業に勤めても、目的やスピード感などが異なり、うまくかみ合わないことが多々あります。そうした課題感から、まずはライトな形で企業と研究者の交流、お互いのギャップを知る機会を増やすことが必要だと考え、2020年に元研究者の知人と一緒にA-Co-Laboを立ち上げました。

藤谷:大学における研究者の正規雇用と非正規雇用の割合は、どれくらいなのでしょうか。
原田:いくつか調査結果はあるのですが、おおむね4割〜6割ぐらいが非正規雇用といわれており、その多くが40歳以下の若手研究者です。しかし30~40代は、プライベートでも結婚・出産など大きなライフイベントやキャリアの変化のある時です。そんな時期を迎えてキャリアを見直し、大学を辞めて企業に就職しようと思っても、社会の仕組みや企業のルールなどを知らないと一歩が踏み出しにくい。そうした面をA-Co-Laboでサポートしたいと考えました。
技術者・研究者と企業が、マッチングに求めていること

——現在A-Co-Laboに登録する技術者・研究者の皆さんは、どんなニーズをお持ちの方が多いんですか?
原田:自分が学んできた技術や研究をほかの場所で生かしてみたい、所属している研究所では経験できないことにトライしてみたいなど、新しい分野での挑戦を望んでいる方が多いです。加えて副業や兼業など、新しい働き方に関心が高い方も多くいらっしゃいます。
——逆に、A-Co-Laboに技術者・研究者の紹介を希望する企業は、どんなことを求めているのでしょうか。
原田:いま、多くの企業は速いスピードでイノベーションを創出することが求められていますが、ゼロからイチを生み出すことはなかなか難しい。そこで、社内では浮かびにくい、新しいアイデアのヒントを一緒に考えてくれる存在を探して「A-Co-Labo所属の技術者・研究者でよい人いませんか」などとご相談くださる企業が多いです。
藤谷:確かに企業側からみると、自社事業とはまったく離れた分野の技術者・研究者を、単独で探すことはなかなか難しいですね。しかし、イノベーションのカギはそうした異分野の知見のかけ合わせですから、A-Co-Laboのような、間を取り持つ存在があることはすばらしいと思います。
原田:ありがとうございます。技術者や研究者は、自身の知見や技術のコア部分について、所属機関の守秘義務の関係で公に発信できないことも多くあります。
そこでA-Co-Laboでは、秘密保持契約などの適切な枠組みを前提に、研究者と企業の安心できる対話環境を整えています。これにより、人材・企業・分野の壁を越えて、知見を適材適所に活用できる仕組みづくりを進めていければと考えています。
技術者・研究者の、新たな領域への挑戦をサポートするには?

藤谷:原田さんのお話をうかがっていて、ある程度キャリアを重ねた技術者・研究者の方々が、新たな場や領域でチャレンジをすることを阻む”壁”をなくすような、より柔軟なコミュニケーションの場や、交流を活性化する仕組みがあると望ましいのだろうなと感じました。たとえば、共同研究などをしながら時間をかけて理解し合えるような。
末廣:そうですね。ソニーグループ内の取り組みになりますが、似たような考え方のキャリア開発の仕組みがあります。「キャリアプラス制度」といって、所属する部署から異動することなく、本来の担当業務を続けながら、業務時間の一部を別の業務に充て、兼務することができる制度です。キャリア展開の選択肢を広げたり、他部門で自分の専門性を生かしたりしてもらうことをめざしています。
もともと、ソニーグループ内では「自分のキャリアは自分で築く」という考え方が根付いており、自分のやりたい業務やポストに手を挙げて応募する「社内募集制度」なども長年多く利用され、人材の動きは活発なんです。ただ「キャリアプラス制度」は異動しなくていいので、新たな領域への一歩が踏み出しやすいですし、新たな気づきを本来の業務にも生かせるメリットも大きいです。
原田:とてもよい仕組みですね。大学にも、国が推進する「クロスアポイントメント」という、⼤学に所属しながら企業に出向して兼業することを促す制度があるのですが、⼤学側の負担が増えてしまうこともあり、思うように導入が進んでいないのが現状です。こうした動きがもっと活発化するといいなと考えています。
——ありがとうございます。次回は「理系人材に求められる成長」、そして「企業はその成長をどのようにサポートすべきか」などについてお話をうかがっていきたいと思います。
この記事にリアクションする