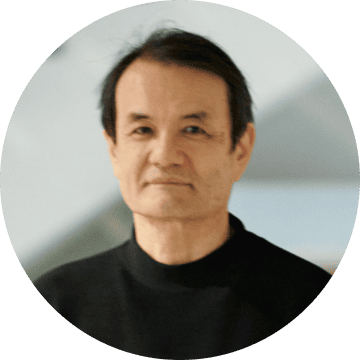Contents
多様性の真価が問われる時代に、山中俊治と考える「マス・カスタマイゼーション」
01
2025.03.25
- Text
- :野口理恵
- Photo
- :平郡政宏

ライフスタイルや価値観の多様化が進む現代、個々に合わせた製品を多数に届ける「マス・カスタマイゼーション」の重要性が増しているのではないでしょうか。デザインエンジニアの山中俊治(やまなか・しゅんじ)さんは、機能性・美しさ・人間工学を融合させたプロダクトを数多く手がけつつ、長年このテーマに取り組んできました。
本企画では「ものづくりの民主化」が可能にしたマス・カスタマイゼーションを入り口にして、誰もが技術やAIにアクセスできる時代の専門家のあり方やこれからのものづくりについて、山中さんと考えます。
第1回ではマス・カスタマイゼーションとは何か、そして山中さん自身の実践について聞きました。
「マス・カスタマイゼーション」は、多様性を尊重しながら、個々のニーズに合わせた製品を低コストで大量生産する仕組みです。山中俊治氏は、3DプリンターやCADなどのデジタルファブリケーション技術の進化により、これが実現可能になったと語ります。彼が手掛けた「美しい義足」プロジェクトでは、職人の技術をデータ化し、効率的にカスタム義足を制作することに成功しました。これにより、個別対応しつつ多くの人へ提供することが可能になり、義足を「かっこいいもの」ととらえる新しい価値観も生まれました。技術の進歩が「ものづくりの民主化」を促し、マス・カスタマイゼーションの時代を切り開いているのです。
マス・プロダクションからマス・カスタマイゼーションへ
――多様性の尊重が注目されるようになった近年、「マス・カスタマイゼーション」に対する需要もまた高まっています。山中さんはデザイナーとして長年このテーマに取り組んできた方ですが、改めて、マス・カスタマイゼーションとは何でしょうか。
山中:マス・カスタマイゼーションは、一人ひとりのニーズに合わせた製品を、大量生産と同じくらいの低コストで製造することで、多くの人に届けることができる仕組みのことです。
20世紀初頭からマス・プロダクション(大量生産)により、均質なものが誰でも手に入るようになりました。アメリカの芸術家であるアンディ・ウォーホルが「大統領もリズ・テイラーもホームレスも同じコークを飲める。すべてのコークは同じで、すべてのコークはおいしい(※)」と著書に残しているように、この時代は同じものを大量につくることがすべての人びとをハッピーにすると信じられていたんです。
ところがやがて、マス・プロダクションの限界が見えてきます。標準的なものを大量生産すればハッピーになれるという理想に対して、現実には結局ローカライズが必要だったり、マイノリティの存在を考慮していなかったりと、大量生産というのは実はさまざまな問題を抱えながら人びとの権利を圧迫していることに、皆が気付き始めました。

――大量生産されたプロダクトに人が合わせるというスタイルに限界がきたということでしょうか。
山中:ユートピアだと思っていたものはユートピアではなかったんですね。同じものを大量に作ること自体が、人類が均質であることを要求していたとも言えます。そこで、「マス・カスタマイゼーション」が重要だと言われるようになりました。
さらに20世紀後半になって、「ものづくりの民主化」が起こります。2010年代以降、「メイカーズ・ムーブメント」は日本でも大ブームになりましたよね。デジタルファイルやCADや3Dプリンターを活用した「デジタルファブリケーション」が浸透して、誰もがものをつくることができる時代になり、インターネット上で情報を発信・共有して皆で製造に参加できる「ソーシャルファブリケーション」という言葉も生まれました。
こうした流れは、マス・カスタマイゼーションの実現を大きく後押ししました。個人がデジタル工作機械を使い、多様なニーズに合った製品を、それぞれでつくり出せるようになったのです。
マス・カスタマイゼーションを技術の進歩が可能にした
――山中さんがこれまで携わられてきたプロジェクトで、マス・カスタマイゼーションを強く意識したものはありますか。
山中:2008年からスタートさせた、アスリートのための義足をデザインする「美しい義足」プロジェクトですね。この3Dプリンターでつくる義足のプロジェクトは、東大の3Dプリンティングの専門家である新野俊樹先生を中心に、SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)の助成金を得ながら進めました。

山中:基本的に義足は手づくりベースで、体の型を取り、微妙に調整しながらつくっていくものです。それまでは経験を積んだ職人でないとつくることはできないと言われていました。そこに3Dプリンターを持ち込み、彼らと一緒に新しいCADソフトを使ってつくり始めたんですが、これがなかなか難しい。腕のいい職人がつくったものにはなかなか及ばないんです。
ただ一方で、3Dプリンターを使うことで簡単に試作品をテストできたり、CADを使って職人の技術力をデータ化し、記録に残すことができるようになりました。義肢装具士さんたちの作業も設計が主体となり、制作の多くは3Dプリンターに任せられるので作業時間の短縮にもなりました。すでに複数のユーザーに対して提供できているので、これはマス・カスタマイゼーションを具現化できた一例かと思います。
――美しい義足の登場によって、義足を「かっこいいもの」ととらえる新しい価値観も生まれたのではないでしょうか。
山中:私は南アフリカの義足アスリートであるオスカー・ピストリウスが世界大会で走る姿を見て、こんなに人間と連動してきれいに動く人工物が存在するんだと感動し、義足というものに興味を持ちました。日本でスポーツ義足をつくる数少ない義肢装具士、臼井二美男氏に会いに行き、義足の練習者たちとも語り合い、そこであらためて「義足はちゃんとデザインされていない」ことに気がつきました。
一般的に「デザイナー」という言葉から連想されるのは、製品の外観をデザインするスタイリングデザイナーでしょう。後で詳しくお話ししますが、スタイリングデザイナーというのは大量生産を前提として成立する職業なので、一つ二つのものをデザインしてもビジネスになりません。だから義足はデザインの対象として見過ごされてきました。主に本物そっくりであることだけが、外観に対する要求だったのです。
産業として成立するかどうかはともかく、「美しい義足」は存在しうると感じたので、まずは慶應義塾大学に設立したばかりの私の研究室で義足のデザインを始めてみました。時を同じくして、片足義足のアスリートである高桑早紀さんに出会います。彼女が足を失った後、走る練習を始めたばかりの頃でした。高桑さんは高性能できれいな義足に興味を持ち、やがて慶應の研究室に入ってきてくれて一緒に義足をつくることになりました。
本人の努力が実って彼女は日本記録保持者になり、のちにロンドン、リオ、東京パラリンピックに出場しました。彼女がかっこいい義足で世界大会に出てくれたおかげで、この義足の存在が世の中に伝わり、自分もつくりたいという人がたくさん現れたんです。そういう意味では先駆的な仕事ができたと思っています。

――最初はたった一人に合わせてデザインした義足だったんですね。
山中:慶應で研究していた頃の義足づくりは「マス・カスタマイゼーション」ではなく、単なる「カスタマイゼーション」でした。高桑さん以外の人に「私も欲しい」と言われても、対応できなかったのです。その後私が東大に移って新野先生に出会ったことで、半自動で個々人に合わせて義足をデザインできるソフトウェア開発が可能になりました。カスタムメイドのものをマスに広げる手段として、3Dプリンターはおおいに役立ったと思います。
――3DプリンターやCADなどのデジタルファブリケーションツールの発展が、マス・カスタマイゼーションの実現に寄与してきたんですね。次回はこうした「ものづくりの民主化」が半導体にまで及ぶ可能性や、技術が民主化されていく時代に専門家の役割はどう変わるのかといったお話を伺います。
※アンディ・ウォーホル『The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again』(1975年)より編集部意訳
この記事にリアクションする