Contents
「お留守番」高山羽根子
01
2024.08.02
- Text
- :高山 羽根子
- illustration
- :Midjourney

半導体技術者のイメージを起点に、技術の魅力を知るきっかけの物語を生み出すことはできるのか。そんな狙いのもと、「記憶」や「孤独」をテーマにした作品で活躍されている高山羽根子(たかやま・はねこ)さんにご協力いただきました。
まず、高山さんとソニーセミコンダクタソリューションズ(以下、SSS)グループのセンサー開発者たちで座談会を実施。その後、高山さんに10年後の未来を舞台にした3つの作品を書きあげていただきました。(座談会はこちら)
最初にお届けするのは、「五感や感情の共有」を描いた物語。イメージング&センシング技術の進化によって、人生の経験を拡張していく生活が実現されることはあり得るのでしょうか。
お留守番
「ただいま」というのは、「ただいま帰りました」の「帰りました」の部分のほうが省略された言葉だ。日本語の慣用表現において重要な情報のほうが省略されることばというのはいくつかあるけれど、いっぽうで「お帰りなさい」のほうは、誰であっても変わらずに帰ってきたという情報だけを発話する挨拶になる。こういう慣用的な略語の意味は、機械に把握させることがとても難しいのだと聞いたことがある。
この国で使われている多くのセキュリティサービスは「ただいま」と「おかえり」という音声コードを起点に構成されているという。
彼がマンションの部屋の前に立ち「ただいま」というと、その声紋を認証して部屋のロックが解除される。
「おかえりなさい」
「旅はどうでしたか」
大きなバックパックを扉の近くに置いてひとつ伸びをした彼は、リビングに入るとポケットに入った”キオク”を部屋の端末に置いた。
「コーヒー、入ってますよ」
というオルスバンの声に、彼は、
「ああどうも」
というような声をあげてキッチンに向かい、ポットからコーヒーを注ぐとリビングに戻ってきてソファに座る。すでに端末は起動していて、キオクによって保存されていた彼の旅が室内に投影され始めていた。
部屋を出て、階段を下りてマンションを出る。駅までの道を進み、電車を待つ。大きめの駅で降り、リムジンバスで空港に向かった。オンラインチェックインは済んでいたので、空港でゆっくりコーヒーを飲みながら読書をする。
「この本、まだ読んでなかったんだ」
「本、読むの遅いから」
入国審査は事情によりスキップ。機内食はケイジャンチキンとショートパスタ、ズッキーニのグリル、ハムの入ったレタスサラダとキャロットケーキ、小さなヨーグルトとクラッカーがついていた。
「概念としての機内食って感じですね」
「未来の食事っぽくてあんがい好きなんだ。こういうの」
現地の空港を出ると、日は暮れていた。タクシーや乗り合いマイクロバスの客引きは、すこしでも目立つようにLEDや薄い液晶を仕込んだ看板を持っているけれど、みなそうやっているのでかえってどれがどれやらわからない。
「暑かったんですね」
「ただ湿度はそれほど高くなかったかも」
「賑やかな国」
「中心からすこし外れれば大自然だけどね」
その日は乗り合いバスで中心部のホテルに泊まり、翌日からの長距離の鉄道旅に備える。砂漠の真ん中を突っ切るように進む鉄路を寝台列車で何泊もしながら進むことになる。
ホテルの前の通りは夜市になっていて、麺も飯もなんでも食べることができた。提灯の中にも、ネオン看板にもすべて同じLED光源が仕込まれているはずなのに、その光の種類は多様で複雑だった。夜市の暗がりには大きな野良犬が眼を薄緑に発光させ、舌を出し浅い息をしている。眼の光はLEDでもないのに、ぎらりと夜市の湿度に濡れたように光っている。
「こんな大きい野良犬、日本にいたら大騒ぎになりそう」
「あの国の夜の暗がりには、そんな生きものがたくさん、ひしめいてた」
蒸篭の積みあがる屋台の席に着き、羊肉の餡が入った茹で包子でビールを飲むと、あっという間に眠気が襲ってきた。考えてみれば、時差も考えると16時間は起きていたことになる。頭上に並ぶ赤い提灯や看板の文字が眠気で滲む。いろんな料理のにおいが混じって体の周りにまとわりついていた。耳に入るのは、意味の分からない、でもきっと楽しいのだろう笑い声交じりの会話。
一旦停止させ、彼は言う。
「まあ、ひとまずこんな感じ。クラウドにコピーはすんでいるから後でこの続きを見てもいいし」
「後でひとりで、ここまでのを何度か見直したいですね」
「ああ、そうだ」
彼は立ち上がって、バックパックのほうに向かって戻りながら言う。
「現地の酒を買ってきたんだ、小瓶だけど」
「わあ、うれしいです。その場所で醸されたお酒を飲みながらその場所を旅できるなんて、なんて贅沢」
オルスバンは声を弾ませた。彼は荷物から取り出した瓶をキッチンカウンターに置き、ラベルを見せながら、
「俺はもうすぐ休むけど、準備だけしておく。ロックでいいかな。現地ではホテルやレストランではロック、街中ではストレートで飲んでる人もいたかも」
と、棚からグラスを出し、フリーザーの氷を入れた。酒を注ぎ、リビングにいるオルスバンに手渡す。受け取りながらオルスバンは、
「留守中の情報はそのつど送っていますが、クラウドにまとめてありますので、お休みのあとで確認しておいてください。動画もタイムラインのタグを付けてありますので、お好みの倍速でご覧くだされば」
と言った。
「助かるよ。ありがとう」
「私には旅の体験の共有が、あなたには留守番が必要なわけなので、お互い様です」
「俺はあなたから留守中のこの部屋に起こったさまざまな情報をもらい、俺はあなたに旅の情報を渡す。こうしてキオクをシェアして経験が重なることで、家に居た世界と旅をした世界、どちらの世界も生きたことになる」
オルスバンは、グラスの酒をひと口飲んで、かすかに顔をしかめ、
「旅に出ることが叶わない私にとって、そのことはとても重要です。たくさんの景色を、あなたの目を経由して私の目に焼き付けることができるので」
とこたえる。
「中世とかなら、この行為はきっと、本によって行われたんだろう。聖書にある奇跡とか、オデュッセイアみたいな」
「数十年前でさえ、私たちはほんの小さい「写メ」で見た記録をやり取りしていたわけですから」
オルスバンがそう言いながらテーブルに置いたグラスの氷が、コロリときれいな音を立てる。
「おやすみなさい」
解説

河野:この作品で描かれた世界の実現には、SSSのイメージング技術が「キオク」のキーテクノロジーになるでしょう。旅行に行った体験をそのまま家に持ち帰るため、五感に訴えかける映像を綺麗に撮って投影できる技術の存在が前提です。もう少し先の未来だと、映像を具現化するテクノロジーが発達している可能性もありますね。
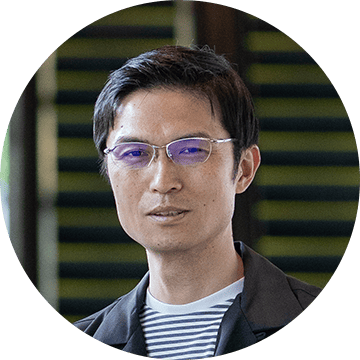
松浦:グラス型なのか、裸眼で体験するかはさておき、空間に映像を投影する技術は進歩していくでしょうね。

河野:もう一つ、作品を読んで思い描いたのが、オルスバンがオデカケにもなる世界です。 物語と反対に、時には人間が留守番をし、オデカケが外の世界を体験してくれる。そんな世界も実現するかもしれません。
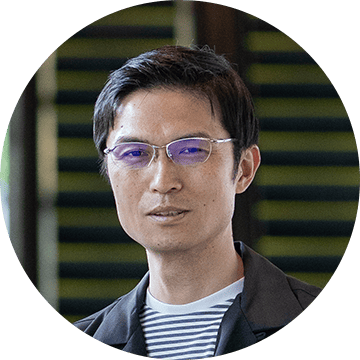
松浦:なるほど。河野さんがおっしゃるように、人間ではない存在が旅をして外出できない生身の人間にその記憶状況を共有する、それは私たちの技術の延長線上にある未来として想像しやすいですね。
この記事にリアクションする











