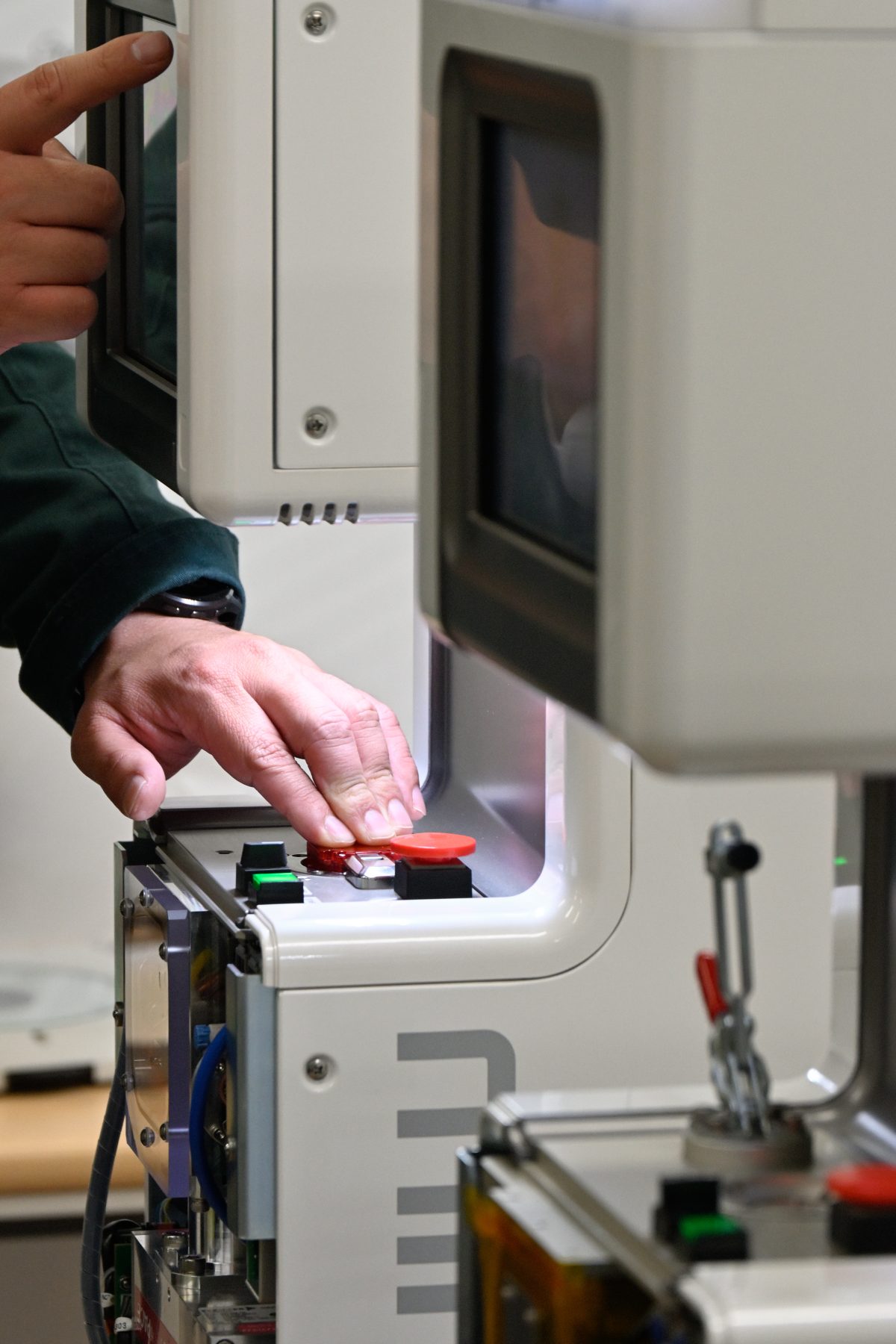Contents
「いつでもどこでも、より自由に」技術の進化で創作の裾野を広げたい
02
2025.02.28
- Text
- :鷲尾 諒太郎
- Photo
- :平郡 政宏

テクノロジーの発達は、いかにして「表現者」をサポートできるのか。前回はダンサー/振付師/映画作家である吉開菜央(よしがい・なお)さんの映像制作の原体験から、イメージセンサーが映像表現に与える影響について、吉開さんとソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(以下、SSS)で主にミラーレスカメラ向けのイメージセンサーを開発している上村晃史(うえむら・こうし)さんが語り合いました。
それに続く今回のテーマは、「人間が持つクリエイティビティの発露を促すために、テクノロジーには何ができるのか」です。
ダンサー、振付師、映画作家の吉開菜央さんは、映像制作におけるテクノロジーの重要性を強調します。彼女は、かつては「カメラでなければ見えない画」を追求し、意図的にノイズを使った作品も制作していましたが、やがて「見たままの画」を求めるようになったと語ります。
また、吉開さんは防塵・防滴機能や低光量での撮影能力を重視し、これらがクリエイターの表現の幅を広げる要素であると述べています。上村さんは、編集容易性を重視した技術開発を行っており、例えば8Kイメージセンサーも編集作業を円滑にすることに寄与しているものであると説明します。議論の中で、映像制作の民主化が進む中、技術が創作活動を支える基盤となっていることが強調されています。
「カメラでなければ見えない」と「見たまま」の間。技術と創作のつながり
上村 前回は、創作活動のきっかけとして映像編集ツールの存在が大きな役割を果たしたというお話をうかがいました。その中で、吉開さんの作品づくりへのこだわりについて少し触れたのですが、もう少し具体的に映像表現の際に意識していることはありますか。
吉開 もともとは「カメラでなければ見えない画」を撮ることが好きでした。たとえば、ピントが合っていないときのボケを利用して抽象画のような画を撮ったり、ズームをし過ぎてぐちゃぐちゃになってしまった画をそのまま使ったりもしていました。あえてノイズを発生させることもありましたね。

上村 映像表現としてノイズを故意に使われているんですね。
吉開 かつて、記録媒体としてminiDV(小型ビデオカメラに直接セットして、映像を記録できるビデオテープ)を使用していたときは、よくその表現をしていました。撮影した時点ではそれほどでもないのですが、編集段階でノイズが入ることがあったんです。それがおもしろいと思って、そのまま残すこともありました。
上村 まったく他意はなく事実としてなのですが、私たち開発者はノイズを極限まで減らす努力をしているんですよ(笑)。その視点からすると、ノイズを映像表現に用いるというのは新鮮ですし、興味深いですね。
吉開 すみません(笑)。デジタルで撮るようになってからは、意図的にノイズを残すことはなくなり、むしろ前回お話したような「見たままの画」を撮りたいと思うようになりました。それも、カメラの進化による影響が大きいと思います。これも言い訳ではないですよ!
制作の際は、私自身が撮影することもあれば、ビデオグラファーやシネマトグラファーさんに入ってもらうこともあるのですが、いずれの場合でもかなり少人数で制作しています。そういった体制でも、映画館の大きなスクリーンでの上映に耐えうる画質で映像を撮ることができるのは、ひとえに上村さんたち開発者の皆さんのおかげですね。
上村 私たちがめざしているのは、クリエイターの裾野を広げることなんです。誰でも簡単に、自らが思うような表現をしてほしい。そう思って日々開発に臨んでいるので、そう言っていただけるのは本当に有り難いですね。
「編集容易性」とは。技術者が語るクリエイターのためにできること
上村 ちなみに、カメラに対して、こういった機能や要素があればもっと表現の幅が広がるのにと思うことはありますか。
吉開 防塵・防滴機能ですかね。以前、別の監督の作品に参加させてもらったとき、かなり雪が降っている環境で撮影していたんですよね。自身の作品でも、そういったやや過酷な環境で撮影をすることもあるのですが、そのときいつもカメラが壊れてしまわないか不安になって……。
上村 イメージセンサーについて言えば、過酷な環境での使用を想定して設計し、耐久性に関するテストを繰り返しているので、厳しい環境下でも壊れないようになってはいます。もちろん、カメラ自体の耐久性や防塵・防水機能とは別なので注意は必要なのですが。細かな条件については、各カメラメーカーに確認すれば教えてくれると思います。
吉開 なるほど。ちょっと確認してみます。どのような環境でも、安心してシネマライクな映像が撮ることができるようになれば、とてもすてきなことだなと思います。先ほど「クリエイターの裾野を広げたい」とおっしゃっていましたが、技術面で進めていることなどあったりするのでしょうか。

上村 「暗いところでも、照明なしで映像を撮ることができるようにすること」はその一つですね。大規模な撮影であれば、基本的に照明を使用されるケースがほとんどかと思うのですが、単独で作品づくりをされている方、あるいは少人数のチームだと難しい場合も多いかと思います。なので、少ない光量でもきれいな映像が撮れることをめざしてイメージセンサーを開発しています。
また、電力消費を抑えることも重要です。イメージセンサーの電力消費量はカメラ全体の中でも大きな割合を占めるので、そこを削減することで、バッテリーの駆動時間が延びてより長時間の撮影が可能になります。
吉開 それはうれしいですね。たとえばドキュメンタリーの撮影では、いつ重要なシーンが訪れるかがわからないので、カメラは常に回しておきたいんですよ。バッテリー交換の間に、残すべき会話が交わされてしまうかもしれない。そう考えると、撮影可能な時間を延ばすのはとても重要ですね。
上村 そしてなにより「編集しやすい映像が撮れること」ですね。私たちは「編集容易性」という言葉を使っていて、開発における指標の一つになっています。たとえば、私たちは8Kのイメージセンサーを開発していますが、そこまでの画素数が必要なのかと疑問をいただくこともままあります。でも実はこれ、編集容易性も考えてのことなんです。
もちろん、8Kのまま使用してもらうことも大歓迎なのですが、「トリミングしても4Kで使えるからとりあえず大きく8Kで撮っておこう」など、どちらかと言えば撮影後の編集の段階で、取り回しよく使っていただけるかを念頭に置いています。

吉開 本当にその通りで、ファインダー越しというか、その場でどれだけいい画が撮れるかが一番大事というのはもちろんなんですけど、編集のしやすさはあればあるほどいいので(笑)。
上村 そうですよね。やはりまわりでも、撮影よりも編集に時間がかかっているという方が多いので、解像度から色彩の調整などを含めて、編集しやすいデータを残せることは大事だなと。
動画を撮る人が増えたからこそ、編集容易性の高い環境を提供することが、「表現の民主化」を進める鍵になると思っています。
では、自分が言っておいてなんですが、映像制作の民主化につながる話が出たところで、次回は「テクノロジーとクリエイティビティのこれから」についてお話しさせてください。
この記事にリアクションする