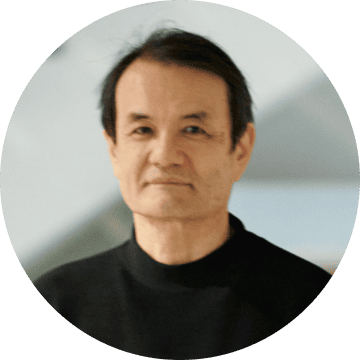Contents
技術の民主化がもたらすものとは。再定義される人間のクリエイティビティ
02
2025.03.25
- Text:
- :野口理恵
- Photo:
- :平郡政宏

21世紀に入って、3Dプリンターなどのデジタルファブリケーション(デジタルデータに基づいて素材を加工する製造技術)により、個人が自由にものづくりにアクセスできる「ものづくりの民主化」が進みました。同様に「半導体の民主化」によって、半導体までも個人が自由にカスタムできるようになるかもしれません。
こうした時代に、ものづくりや専門家のあり方はどう変わっていくのでしょうか。AIには再現できない、人間のクリエイティビティの本質とは?
ものづくりの力で社会に革新的な変化をもたらしてきたデザインエンジニアの山中俊治(やまなか・しゅんじ)さんに話を伺いました。
デザイナーエンジニアの山中俊治氏が、「半導体の民主化」がものづくりやデザインに与える影響について語ります。1990年代、高価で入手困難だった半導体チップを使うために研究所と交渉していた経験を振り返りつつ、2000年代にはプログラマブル・チップの普及により、動くプロトタイプが作れるようになったことを指摘します。もし半導体設計まで自由にできる時代が来れば、ハードウェアとソフトウェアの統合が進み、さらに柔軟なものづくりが可能になるでしょう。技術の民主化によってプロの価値が失われるのではなく、むしろプロの視点やスキルがより際立つと強調。AIが席巻する時代にあっても、人間ならではの経験や感覚がクリエイティブなものづくりの源泉であると語っています。
もし半導体までカスタムできたなら、ものづくりやデザインはどう変わるのか
――メイカーズ・ムーブメント以降、「ものづくりの民主化」が進みました。今、「半導体の民主化」の可能性すら視野に入ってきています。半導体チップと山中さんのものづくりの関わりについて教えてください。
山中:1990年代は大学の研究室ではなく、自分の会社であるリーディング・エッジ・デザイン(1994年設立)で仕事をしていたのですが、若い方から「こういうプロトタイプをつくりたいので、このチップを手に入れたいんです」という相談をされたことを覚えています。
当時の半導体チップは小ロットでは買えないし、そもそも高価なので、「サンプル品をもらえないか」とあれこれ研究所に相談して、ようやく使えそうなものを見つけました。当時は工業製品を新しくつくろうと思っても、実際に動くものにするのはそう簡単ではなかったのです。

山中:それが2000年頃から汎用のプログラマブル・チップが急速に普及し、研究員たちが秋葉原で買ってきた部品でワーキング・プロトタイプ(実際に動作する試作品)をつくれるようになりました。絵に描かれたモックではなく、動くものを実際に触って検証できるようになったんです。当時参加してくれた若者たちはソフトウェアもハードウェアも自作するスキルがあり、この頃からものづくりの体制が大きく変化した実感があります。
こうした「ものづくりの民主化」によって、それまで手づくりでは到底つくることができなかったレベルの複雑さと精巧さが私たちに解放されました。そうなると、デザインする際にも「このレベルのものは自分たちで手づくりできるのではないか」という思考に変化していきます。
今、私の研究室では「自分たちである程度動くものをつくる」のが当たり前になっています。大量生産の時代からものづくりの民主化を経て、自分たちでプロトタイプをつくることができるようになったという原体験が、私の「マス・カスタマイゼーション」に対する考え方のベースにあると思います。
――半導体の設計から製造まで個人で行うことはまだ難しいのが現状ですが、もし自由につくることができるとしたらどのような変化が起きると思いますか。
山中:カスタマイズされた半導体が欲しいというのはどういう状況なのか、ということから考えてみましょう。ハードウェアについては、外注しなくても3Dプリンターで十分に機能する構造をつくることができるようになり、ソフトウェアの振る舞いについても、バーチャルな世界の中で組み立てることができますよね。そうやってハードウェアとソフトウェアについて検証していって、最後に「このサイズに収めたい」とか「この場所、この人のためにつくりたい」と考えたときに、「こんな半導体が欲しい」という発想になると思います。
それを具体的にどんな姿で思い描けばいいのかは難しいですが、ほかの技術同様に、よく知らない人でも使えるようにプロトタイピングツールが汎用化されていくのも、そう遠い未来ではないのではないでしょうか。さまざまな分野で「プロトタイプ」と「プロダクト」の境目が消えつつあり、半導体でも同じ状況になる可能性はあると思います。

技術やノウハウが開かれていく時代に、プロのあり方は変化するのか
――ものづくりの民主化により、プロとアマチュアの境界が薄まっていくようなイメージがありますが、それによって専門家の価値が低下するようなことは考えられるでしょうか。
山中:ある技術が誰にでも使えるようになったとき、プロの存在意義がなくなるのではないかということが言われがちですが、私はそんなことはないと思います。たとえばデジタルカメラによる「写真の民主化」が起きて、誰もがカメラマンになれる時代になりました。しかし誰もが写真を手軽に撮れるようになった結果、皆が思ったのは「プロはやっぱりすごい」ということです。技術が民主化すると、かえってプロの目やスキルがいかに洗練されているかが際立つ。これはAIにも同じことが言えると思います。
――今、まさに「生成AI」が話題ですね。
山中:AIに関しては、今のところ皆が「そうきたか!」とギョッとするようなものは生まれていません。AIは確実に進歩していますが、結局はクリエイションを極めたプロフェッショナルのすごさがよりよくわかるようになるだけではないでしょうか。ですからクリエイターは、仕事を失う心配をしなくてもいいんじゃないかと思います。
――とはいえ、たとえばデザイナーの仕事自体は変化していくのではないでしょうか。
山中:それは間違いないですね。大量生産時代のデザイナーの仕事は、あるアイデアを量産できて皆に行き渡るような形にすることでした。だからアイデアそのものは何かの焼き直しでもよかった。でも、そういう仕事はAIでもできます。
写真のたとえに戻ると、かつて町の写真館は現像所を兼ねていて記念写真などを撮っていましたが、今、写真家がそれで生計を立てるのは難しい。プロのカメラマンはきれいな写真を撮れるだけでなく、「何かしらの価値をその場で切り取れる人」というのが大事になっています。

――デザインやものづくりにおいて、AIにできないこととは何だと思われますか。
山中:AIにとって一番難しいのは、人生経験を積むことです。もちろん体験のレポートを大量に読み込むこともできるし、それっぽい答えも出せるかもしれませんが、人間一人ひとりが持つような価値観を持つことは、現状はできていません。
デザインやものづくりの源泉は、「私はこういうものが欲しくてしょうがない」「気になってしょうがない」といった個人の感覚だと考えています。そういう感覚は個々の体験に由来するものなので、AIには手に入れることができません。自分の行きたい道の中で「これが最高!」と感じて、ものづくりをして、人びとの共感を得る。これが最もクリエイティブなやり方だと思います。
――自分自身の欲しいもの、やりたいことを大切にものづくりをしよう、ということですね。次回はこれからの専門家のあり方について、さらに詳しくお話を伺っていきます。
この記事にリアクションする